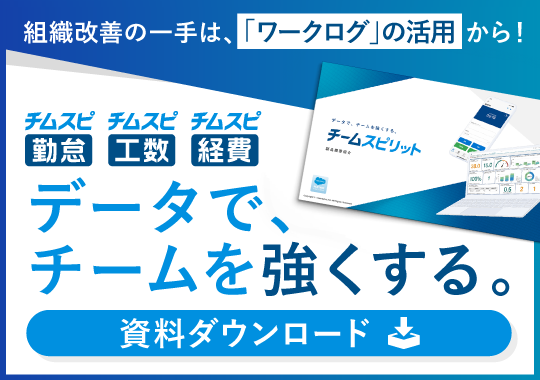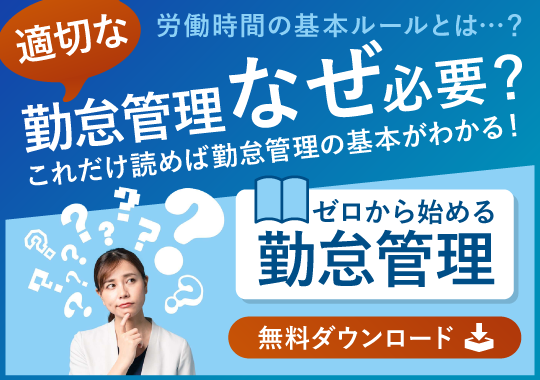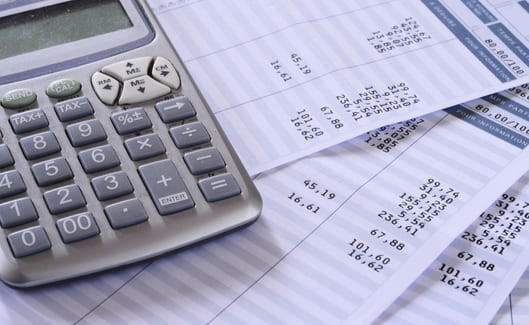チムスピコラム
-
 システムの活用
システムの活用タイムカードの勤怠管理は時代遅れ?メリット・デメリット・注意点などを解説
-
 システムの活用
システムの活用中小企業におすすめの勤怠管理システム13選|目的別の選び方を解説
-
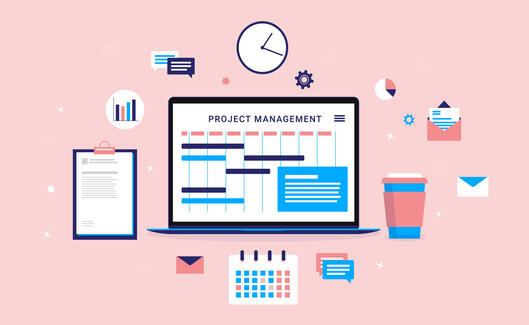 基礎知識
基礎知識プロジェクト会計はどうやる?最重要の原価管理のやり方・ツールも紹介
-
 基礎知識
基礎知識休日出勤させる場合の36協定のルールや罰則【社労士監修】
-
 基礎知識
基礎知識有給休暇の法律と罰則とは?違反しないための対策も解説
-
 システムの活用
システムの活用おすすめの有給管理システム10選|必須機能や選び方のポイントを解説
-
 システムの活用
システムの活用勤怠管理システムの失敗例6つ|導入失敗にならない選び方のポイントも解説
-
 基礎知識
基礎知識勤怠データの分析・活用方法|基礎知識や保管期間も解説
-
 基礎知識
基礎知識労務管理とは|具体的な業務内容や注意点、効率化する方法を解説
-
 基礎知識
基礎知識勤怠締めのやり方や効率的に行う方法・注意点を解説
-
 基礎知識
基礎知識労働時間管理とは?義務化で企業が取るべき対応をガイドラインからわかりやすく紹介
-
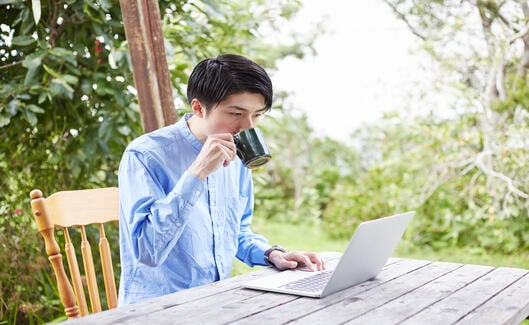 基礎知識
基礎知識法定休日とは?ルールや法定外休日との違い【社労士監修】