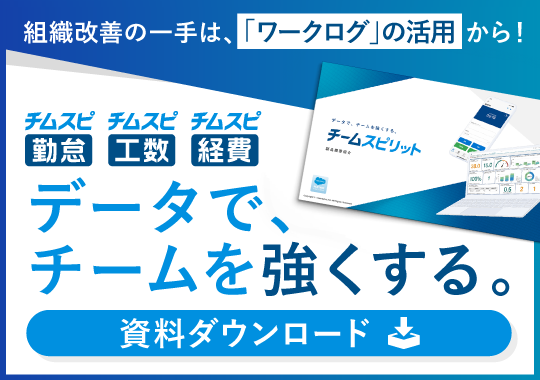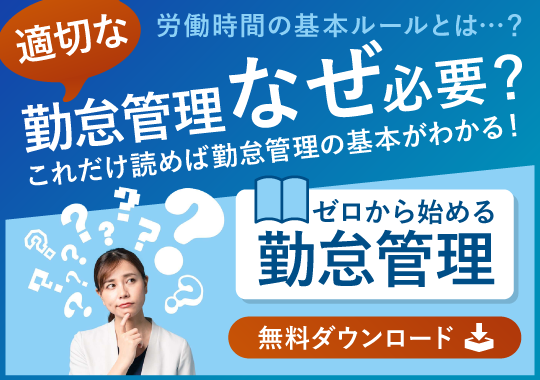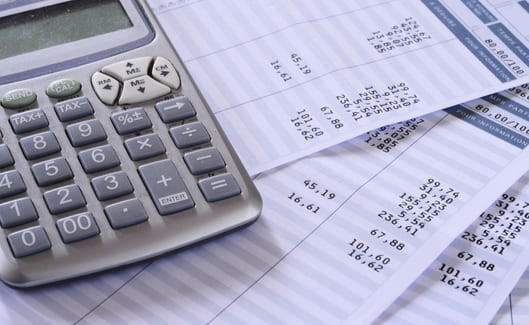チムスピコラム
-
 基礎知識
基礎知識PCログと実労働時間が乖離する理由|乖離発生時の対処法も解説
-
 基礎知識
基礎知識未払い残業代を請求された!在職中・退職後2パターンの対応をそれぞれ解説
-
 業務改善
業務改善給与計算担当者がつらいと感じること5つ|対処法も紹介
-
 基礎知識
基礎知識給与計算ミス発生時の対処法|お詫び文書例や防止策も解説
-
 基礎知識
基礎知識育児介護休業法改正のポイントをわかりやすく|2025年に施行される最新情報
-
 システムの活用
システムの活用勤怠管理システムのセキュリティは安全なのか?対策やツール例も紹介
-
 システムの活用
システムの活用PCログでの勤怠管理とは?メリットや注意点、運用時のポイントを解説
-
 システムの活用
システムの活用給与計算を効率化・自動化する3つの方法|費用や重要ポイントを解説
-
 基礎知識
基礎知識【図解あり】産後パパ育休とは?制度の詳細や注意点、推進方法を解説
-
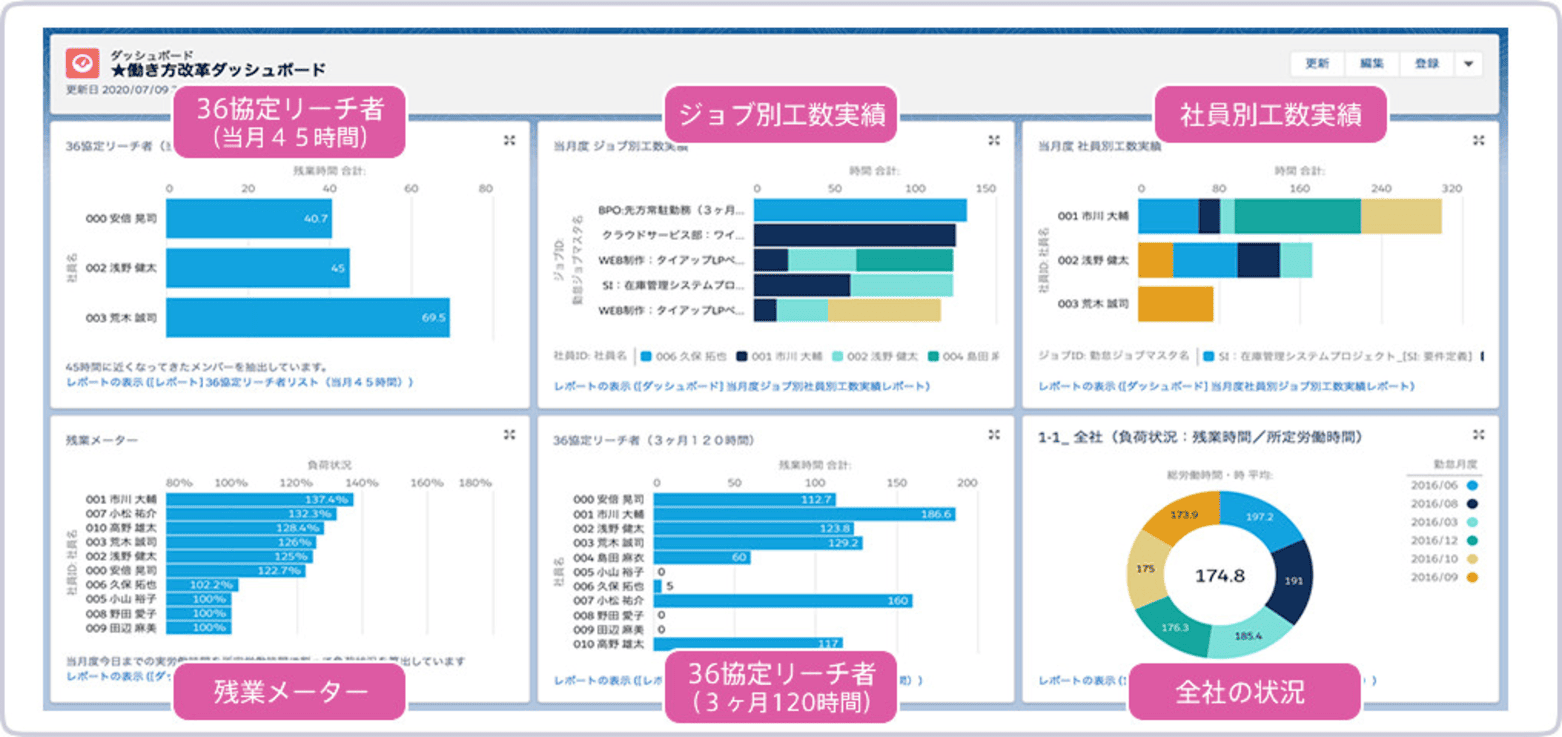 システムの活用
システムの活用チムスピ勤怠の口コミ・評判|導入メリット・注意点などを解説
-
 システムの活用
システムの活用タイムカードと勤怠管理システムはどちらが良い?メリット比較とシステム導入すべき企業
-
 システムの活用
システムの活用中小企業向け勤怠管理システムとは?必要な機能やおすすめ14選