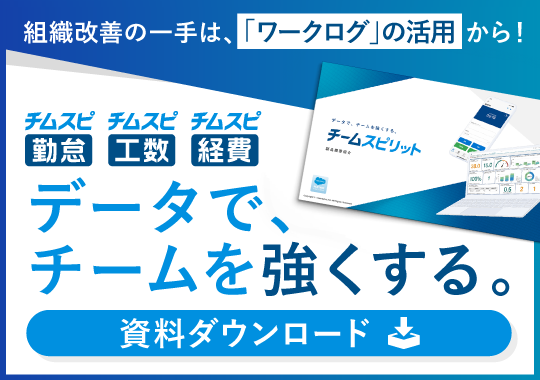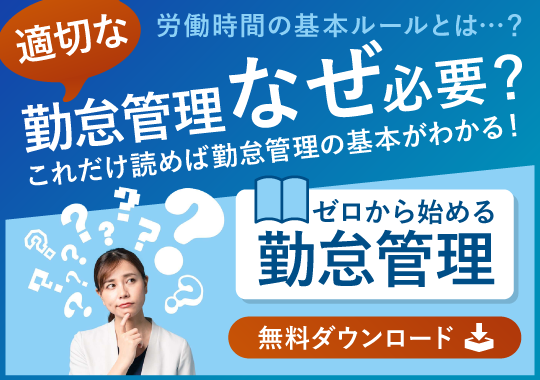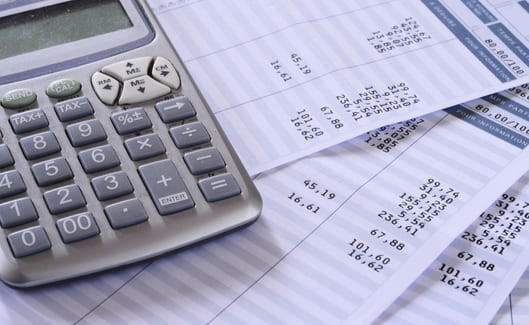チムスピコラム
-
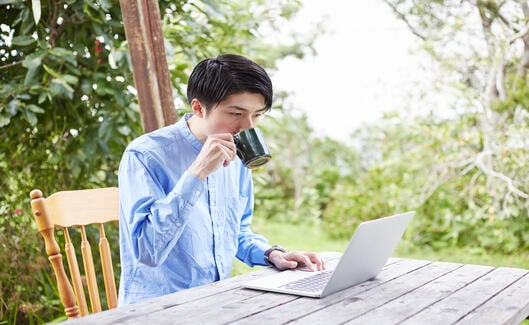 基礎知識
基礎知識法定休日とは?ルールや法定外休日との違い【社労士監修】
-
 基礎知識
基礎知識【図解】有給休暇の繰り越しとは?消滅ルール・上限・計算方法をわかりやすく解説
-
 基礎知識
基礎知識中抜けとは?勤怠管理での扱い方・就業規則の書き方を解説
-
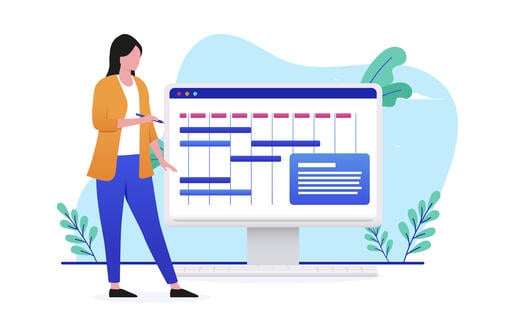 基礎知識
基礎知識時季変更権とは?行使できるケース・できないケースの具体例・注意点を解説
-
 基礎知識
基礎知識計画年休とは?有給との違いや効果・デメリットをわかりやすく解説
-
 基礎知識
基礎知識法定内残業とは?法定外残業との違いや計算方法・具体例を解説
-
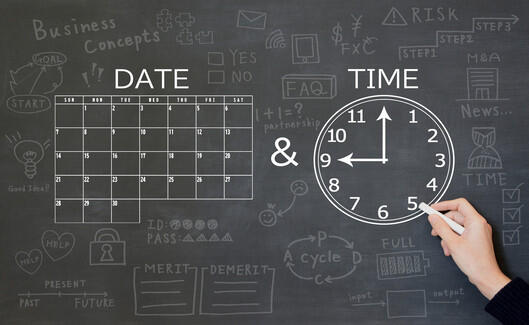 基礎知識
基礎知識【勤怠管理の基礎知識】勤務間インターバル制度とは?
-
 基礎知識
基礎知識「年俸制だから残業代は支払わなくてもOK」ってホント!?正しい「年俸制」導入のポイント
-
 基礎知識
基礎知識【勤怠管理の基礎知識】高度プロフェッショナル制度とは?
-
 業務改善
業務改善【勤怠管理の基礎知識】 1ヶ月単位の変形労働時間制とは?
-
 基礎知識
基礎知識コストセンターとプロフィットセンターの違いとは?どちらを目指すべきか
-
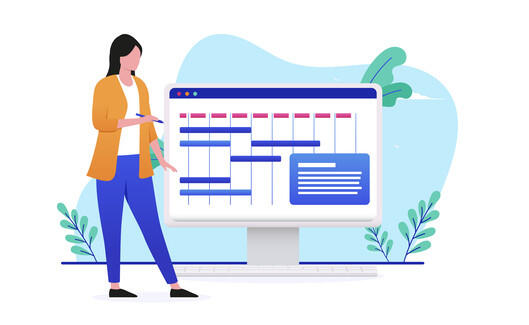 基礎知識
基礎知識【テーマ例あり】1on1で「話すことがない」と部下に言われたときの対処法